大阪の道頓堀川で釣りをしながら水質改善の歴史と現状を探る。ブルーギルやキビレを釣り、美味しく調理。川の生態系と課題を学ぶ。
本日は大阪の有名な観光地、道頓堀川にお邪魔しました。過去には川への飛び込みや基準値を大幅に超える大腸菌の発見など、悪名高いエピソードを抱えるこの川。ですが、実は意外にも多くの魚が生息しています。今回は、実際に釣りを行い、どんな魚がいるのか調査するとともに、釣れた魚の味も楽しみたいと思います。
道頓堀川は、その昔、高度経済成長期から1980年代にかけて深刻な水質汚染に悩まされました。工場排水や生活排水が直接流れ込むことで、魚たちは生息しにくい環境だったのです。しかし、2007年以降、他の綺麗な川から水を注ぎ込む施策により、水質が改善の方向に進みました。それでもなお、川の水は汚れており、釣りをする前に水質調査を行いました。COD(化学的酸素要求量)が「8」という結果から、この川の水質の悪さが浮き彫りになりました。
道頓堀川で釣りをするには、大阪府の道路管理課に確認した通り、釣り可能な場所とそうでない場所があります。今回は特に通行人の少ない、釣り可能なエリアで釣りを行いました。使用した仕掛けは、浮き釣り用の簡単なもので、袖針を使っての釣りです。
実際に釣りを始めると、最初の収穫はブルーギル。水がトロトロしていて、まるで乳液のようでしたが、ブルーギルは1960年代に日本に持ち込まれ、特に栄養価の高い魚として知られています。また、釣れたキビレも、黒鯛に似た魚で、引きが強く釣り好きにはたまらない魚です。水の中で見つけたブルーギルとキビレをその場で調理し、美味しくいただきました。
続く調査では、道頓堀川の上流に向かい、さらに多くの生物を発見しました。様々な生物が暮らす上流から川底まで、水質の浄化に寄与する淡水二枚貝や炭水シミが発見され、水質管理における重要性を学びました。台湾シミの侵入による、日本在来種への影響も考慮しながらの調査となりました。
釣りから帰った後は、釣れたブルーギルを下処理を施し調理。塩水と酢、コーラを用いて臭みを取り除き、料理として楽しみました。最終的には美味しくいただける形に仕上がりましたが、その過程で気づいた道頓堀川の課題と楽しさをお伝えしたいと思います。

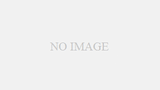
コメント